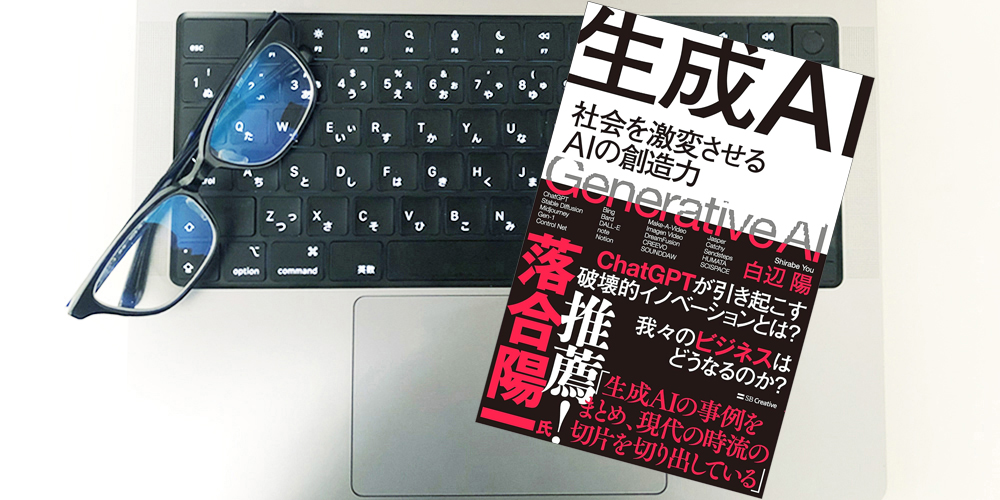
「ChatGPT」や「Stable Diffusion」などの「生成AI」がもたらすビジネスや生活の変化をキャッチし、全く新しいアウトプットを生み出す方法をレクチャー。新しいものを創造するという意味において従来のAIと異なる生成AIについて学んでいこう。
OpenAIの技術は画像生成へも
OpenAIは、文章生成AIで世界中を驚かせました。それだけではなくOpenAIは、この技術が文章生成以外にも応用できることも早期から示していました。
この技術のコアは、前半と後半に分けてみることができます。前半部分は、インプットされたデータをAIが理解できる形に解釈する機能、後半部分はその解釈に基づいて新たなデータをアウトプットする機能です。ここで扱っている「データ」は、テキストデータ、すなわち文章に 限りません。つまり、ここで後半部分で生成するデータを画像にすれば、画像を生成するAI( 画像生成AI)になるわけです。
もともと、AIの進化の歴史の中で、画像を扱うことはずっと、ハードルの高いことでした。文字(テキスト)の情報に比べて、画像データの情報量が圧倒的に多いということがその理由の1つです。スマホで撮影した写真は、撮影方法にもよりますが1枚あたり2MBほどのデータ量となります。これは、テキストデータで言うと約100万文字になるのです。新聞紙に換算すれば約100枚分もの情報量です。
また、データ自体の解釈が難しいということも大きなハードルでした。人間であれば猫の写真を見れば、写っているものがすぐに猫だと分かります。一方で、コンピューターは猫の写真を 色を表したデータの集まり と認識するだけであり、写っているものが何であるかを判別することは難しかったのです。
しかし、AIの技術が発展する中で、画像についても、次第に色々な扱い方ができるようになってきました。
生成AIは普段使いに便利で僕もよく使っています。特に画像の生成に関してはテキストで上手いことイメージを言語化できれば、思いのままのイラストや写真を生成できます。画像編集や動画編集の分野でもこの生成AIがこれからの主流になってくるかと思います。やったことのない人はぜひ試してみて!世界がひっくり返ります。
検索エンジンと生成AIの違い
今使われている検索エンジンは、ウェブ上にある情報の表面を上手く分析して、有用性を判断し、それを検索結果に反映しています。実際に行われていることとしては、世界中の様々な記事のタイトルや本文から、キーワードを抽出してインデックス(目次)に登録し、その記事へのリンクの多さや、過去のアクセス状況等に基づいて、順位付けをして検索結果を表示します。その情報の取捨選択こそが検索エンジンのコア機能だったのです。
だからこそ直近 20 年間は、自社商品をアピールしたい企業側が、検索結果の上位に表示されるように SEO対策 を行い、検索エンジン側が特定企業に有利となりすぎないように、コンテンツの評価基準を見直すというイタチゴッコが続いていました。
一方で、生成AIが評価するのは、情報の表面だけではなく、 情報そのものの全て です。この段階になると、イタチゴッコが基本的に成立しなくなるのです。
これまでSEO対策や広告に依存していた人たちは、なんとかして生成AIの目をかいくぐって、自分の記事を上位に表示させたいと思うでしょう。
初期のうちは生成AIも完璧ではないので、そのような小細工に引っかかってしまうこともあるかもしれません。しかし、生成AIがその能力の真価を発揮するころには、そのような小細工は全く通用しません。利用者が質問している意図を正しくくみ取り、その利用者のニーズに最も適した情報を、膨大な蓄積情報の中からピンポイントで見つけて回答を作るのです。
利用者にとっても、この2つの使い勝手には圧倒的な差があります。
検索エンジンは、いわば 図書館の司書 のような存在です。欲しい情報を伝えれば、その情報が載っていそうな本を提案してくれます。
それに対して、生成AIは 何でも知っている先生 です。
検索エンジンはすでにあるデータを参照し呼び出すのに対し、生成AIは数あるデータの中から新しいものを生成するのに適しています。なんでも知ってる先生に聞いてみる習慣がこれからのスタンダードかと思います。はっきり言って人間に聞く必要がなくなったので、先輩や上司に聞くよりAIに回答を求める方が確実と言った状況。うまいこと使って作業の時短に繋げましょう。
生成AIを触ったことがない方にはぜひ体感してほしい。そんな思いでいます。仕事や趣味が加速するし、創造の幅が広がります。あまりの精度の高さに驚くこと間違いなし!
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




