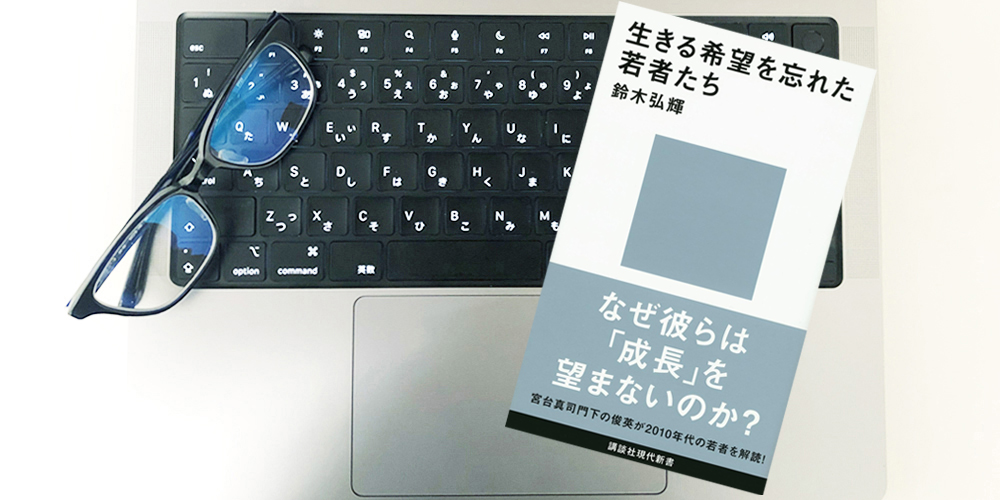
近頃の若者に対する年配者との感覚のズレの正体を探る。若者が「いま」だけを大事にしているように見える理由とは?彼らのコミュニケーションの作法から1970年代以降の日本社会の変動と問題点を鮮やかに描き、「不確実で残酷な世界」を生きるための術を学んでいく。
「若者の○○離れ」をめぐって
最近、「若者の○○離れ」が話題になっているという。試しに、インターネットの検索サイトであるグーグルに「若者 離れ」と入力してみると、それこそ若者がいろいろな物事から離れているとされている。その中には、「新聞、テレビ、雑誌、自動車、野球」といった多くの年長者がこれまで親しんできたもの、あるいは必需品とみなしてきたものから、若者のイメージと結びつきやすい「ゲーム、サッカー、コンビニ」といったものまで含まれている。もっとも、この情報を受けとるだけでは、「では若者は何から離れていないのか」と逆に質問したくなるだろう。
おそらく、実感としてあるがどこまで事実かわからないというのが、現実的な感覚なのではないか。とはいうものの、それぞれの分野で生産・販売に携わっている人々にとって、「若者が自分たちの○○から離れていっている」というのは切実な感覚なのだろう。たとえ、それが明確にデータとして表れていないとしても。
しかし、この若者の○○離れという言い方には、(この本の筆者である私も含めた)年長者たちの焦りが表れていると考えられる。それは、年少者たちが自分たちについてきていない、自分たちの立ち位置を「これが基準だ」と示しても年少者たちが従わないといった感情と言い換えてもよい。あるいは、いままで「これでよい」と思って(漠然とであれ)やってきたことが、若者たちに魅力のあるものとして伝わらないといった感覚が、ここ最近広がってきていると思われる。それは、特に若者を相手にする職業に携わる者の間で、しかも自分は若者とコミュニケーションをとるのに自信があると思ってきた年長者に限って、そのような感覚に強く襲われているのではないだろうか。
若者の〇〇離れという割には案外テレビを見ていたりと実情はちょっと違うような気がしています。昔と比べて選択肢が増えたことによりテレビを見る人が減っただけだと。テレビ番組はスマホで見られるサービスの普及でリアタイにこだわらなければビデオに撮る必要がないので便利ということだろう。
失われた「長きにわたる確実な未来」
このように、「ポスト三・一一」にはかつてのプラスイメージの未来観は不必要であり、そういうものからいますぐに現在の人々が解放されなければならないことが示された。しかし、日本社会の現状は全くそのようになっておらず、そのことに橘は警鐘を鳴らしている。すなわち、現在の日本社会においての最大の問題とは、すでに使い物にならなくなったかつての未来観に、まだ必死になってしがみついていることだというのである。
では、かつての未来観とは、いったいどのようなものなのだろうか。橘によれば、戦後の日本人の人生設計は四つの「神話」の上に築かれてきたという。
① 不動産価格は上がり続ける。
② 会社はつぶれない。
③ 円はもっとも安全な資産だ。
④ 国家が破産することなどありえない。
そして、これらの「神話」を前提とした人生設計は、戦後の経済成長に最適化したものであったというのである。
いつの時代の話ですか?というのが若者の反応だろうが、高度成長していた時代の人に比べて渋い時代を生きたきた若者にとっては当たり前のことがそうでなかったりと年代別で認識の違いが。僕はギリギリでバブル時代を知っている世代なのでその気持ちもわからないではないが、その後の若者は厳しい時代で生きるように。
成長を望まない若者たちの未来感を戦後日本を生きた人たちとの乖離を見ながら論じる書籍。なぜ若者たちは希望を失ったのかがわかる時代感の書籍。
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




