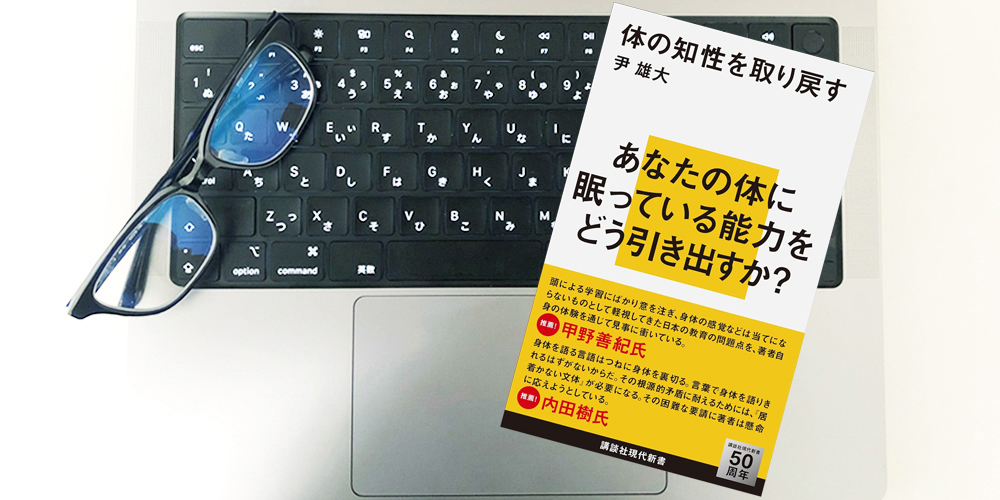
私たちは知らず知らずのうちに社会が求める鋳型に自身の体を矯正して生きてきた。自分の体は自然界最大の謎。あらかじめ備わったその能力を解放すべく、自らの武術体験から眠っている力の引き出し方を明かす。
踏ん張らない、捻らない、タメない
初めて甲野先生を間近に見た印象はと言うと、武道家にありがちな威圧的な雰囲気はまるでなかった。むしろ、マイクを使わなければはっきりと聞こえないくらいの声量で話されていて、武張ったところのなさにかえって好印象を受けた。
講座が始まると、先生は「踏ん張らず、捻らず、タメをつくらずに動く」といった話をされた。常識的に考えると、それらを実行してはまるで使い物にならない動きになる。
たとえば、拳で相手を打とうとするとき、私たちはどうするか。まず拳を後ろに引く。同時に足を踏んばり、腰を捻る。こうして力をためてから、下半身の力を肩、腕、拳へと順々に伝えていくだろう。
どんなスポーツでも、より速く、より強くを目指すならば、しっかりと足を踏ん張り、体を捻ってタメをつくり、そこから腰、腕とうねって力を伝えていくしかないと思われている。しかし、これではどれだけ素早く動いたとしても必ず手続きの時間がかかる。一挙動にはならない。私が経験した限りの現代武道も同様の問題を抱えていた。
古の武士はそんなふうに動いていただろうか。そんな動きでは、相手の刀を避けることなどできない。だから手間暇のかかる常識的な動きをいくら練習しても、およそ精妙な術にはならない。甲野先生はそういう話をされた。
その後、先生が何を説明したかまるで覚えていないのは、その話が別の意味を奏で始めたからだ。私がこれまでの人生の中で拾い上げたり、あるいは捨てようとしてきた事柄がカチリとはまって、ひとつの絵を見せられたような気がした。
武道家の人は案外物静かな人が多い気がします。寡黙で普段から集中しているイメージがあります。踏ん張らず、捻らず、タメをつくらずに動く自然にそんな動きができたら無駄な動きをせずにいろんなことができるので良いのだろう。
言葉以前に体は存在する
自分の意見を述べようとするとき、次のようなことがふと脳裏をよぎらないだろうか。「自分の考えなど既に誰かが言っているのだし、もっと洗練させてから言ったほうがいいのではないか」。
洗練されると、より多くの人を引き込む魅力は増す。同時に、限りなく無難に近づくことにもなりえる。知識や情報を参照し、あれこれと言葉だけで考えていくと、他人が理解しやすい意見に改めていくことと、自分の考えを他人に譲り渡していく工程の違いがわかりにくくなる。
思索していると、知らぬ間に「自分の考えなど大したことはなく、既に誰かが考えたことしか言っていないのではないか」という懐疑が生じる。
己の存在は、そう大したものではないと知っておくことは、傲慢さに陥らないためには必要だ。しかし、「所詮自分などちっぽけなものだ」と卑屈になることも、自分を正当に扱えないという意味では傲慢さの変調でしかない。
武術のよいところは、これらに完全に吞み込まれてしまわないところだ。
たとえ「自分には独自性が乏しい」と思ったとしても、相手が自分に打ちかかってきたとしたら、他人との違いは明確だ。「所詮自分などちっぽけなものだ」と思っていたところで、相手が見逃してくれるわけではない。ちっぽけだろうがなんだろうが、遭遇した事態は自分独自の出来事であり、己で何とかしないといけない。自分という存在、つまり体は、常に個的で他の誰とも取り替えがきかないのだ。
自分の感じていることが、自分にとっての現実だ。したがって人の数だけ現実は存在する。そこに特別さはなくとも、同じ体はふたつとないのだから、極めてオリジナルな見方しかありえない。
つまり、人はそれぞれ独自の見方をしているのだ。
本をたくさん読んでいると、自分の意見なのか、読んで蓄積された知識を引き出しているだけかわからなくなる。今、自分が感じていることをストレートに出せればそれが自分を形成しているものかなとも思います。自分を作るものについては厳選したいですよね。
自分の中にあるものを引き出すために必要なことを教えてくれる書籍。自分のことを形成するものは他人からの受け売りだとしても自分で消化していればOKかと。
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/



