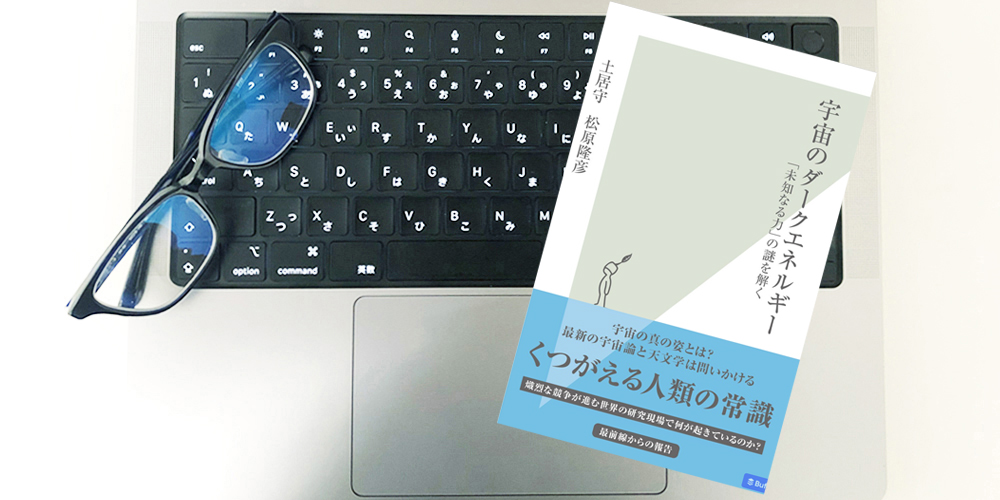
宇宙の膨張は減速どころか加速していることがわかったのが20世紀後半。膨張を加速させる「未知の力」が働いていると考えられるのだが、それは何か?宇宙の真の姿を最新の宇宙論と天文学で解説する知的欲求を満たす一冊。
膨張する宇宙の発見
「方程式は、それを作り出した人よりも賢い」
しかし、前述したように、ハッブルが膨張する宇宙を発見します。膨張する宇宙──それは「宇宙は永遠不変のものである」という、それまでの人類の宇宙観をひっくり返すような発見でした。またそれは、宇宙の姿が刻々と変化しているということを示すものでもありました。
ところがこれは、アインシュタインがはじめに導き出した理論から自然に導かれる現象でもありました。物理学の理論研究では「方程式は、それを作り出した人よりも賢い」と言われることがよくあります。
相対性理論と 双璧 をなす量子力学においても、その基本方程式を導き出したオーストリアの理論物理学者、シュレーディンガーはその解釈を誤っていました。現代では、量子力学が本質的に確率的な本性を持っていることが明らかになっています。しかし、シュレーディンガーはそれを認めませんでした。すなわち、導き出した方程式自体は正しかったのですが、その方程式の生みの親である本人が、式の意味を取り違えていたというわけです。
アインシュタインはいうまでもなく天才ですが、いまから思えばアインシュタイン方程式は、それを生み出したアインシュタイン自身よりもある意味で賢かったと言えます。宇宙項を導入しなければアインシュタインは膨張宇宙の予言者にもなり得たでしょうが、膨張して変化する宇宙というのは彼の信じる宇宙の姿に反していました。
もちろん、宇宙が膨張する証拠もない時代に、永遠不変の宇宙という信念を持つことは自然なことでした。したがって、宇宙が変化するなどという結論が自分の理論から出てくれば、その理論の方を修正しなければならないと思ったのも自然の成り行きでしょう。
実は、膨張宇宙がハッブルによって発見される前、アインシュタイン方程式を使って宇宙のモデルを考えようとする人々はアインシュタイン以外にもいました。
オランダの天文学者、ド・ジッター(図9)は、宇宙にまったく物質が含まれない真空の場合を考えてみて、一般相対性理論により矛盾なく宇宙が存在できるかを調べました(実際の宇宙には物質がありますから、その宇宙モデルは単に数学的なものと考えられます)。また、当時アインシュタインの導入した宇宙項も入れてみました。すると、時空構造の変化しない定常的な真空宇宙を構成できたのです。アインシュタインは当初、宇宙項を使った彼の静止宇宙のみが唯一可能な定常的宇宙ではないかと考えていましたが、そうではなかったのです。
方程式はそれを作り出した人より優れていた。本人はその優れている部分を否定するような答えを提唱することになるが、のちの研究で実際は方程式の方が正解だったのだ。皮肉な話だ。宇宙モデルという壮大な世界を作る方程式と宇宙項。生みの親さえその正確さを誤認していたのだ。
日本のダークエネルギー観測の展望
広視野撮像でリードする日本 それでは日本は今後、ダークエネルギーの研究にどのように関わっていくことができるのでしょうか。先に紹介したように、天文学の広視野撮像の競争において、日本は現在世界の第一線を走っています。さらに多天体分光においても、すばる望遠鏡で計画されている分光装置は世界トップの装置です。振り返ってみると、これは天文学者の努力だけではなく、運にも恵まれ、さらに日本の科学技術が世界の第一線にあったおかげであるとも言えます。
すばる望遠鏡は1999年にファーストライト(望遠鏡が完成し最初に光が入ること)を達成しましたが、当時の8メートル級望遠鏡としてはただ一つ、主焦点を持っていました。米欧の8メートル級の望遠鏡もほぼ同時期に何台も完成していきましたが、望遠鏡の筒先に重たい観測装置を設置することになる主焦点を作ることはしませんでした。なぜなら、そのためには望遠鏡自体をがっちりと作る必要があり、それにはコストもかさみ、また装置交換なども大変になるからです。
これにはちょっとしたエピソードがあります。1990年代、欧米はすでに何台もの4メートル級の望遠鏡を所有していました。このクラスの望遠鏡であれば、宇宙の広い範囲を探索し、8メートル望遠鏡で研究するにふさわしい天体を見つけることが可能でした。
ところが日本は高度経済成長を成し遂げていたにもかかわらず、光学・赤外線天文学観測においては世界に取り残された状態でした。日本が所有する最大口径の望遠鏡は、岡山天体物理学観測所の口径1・9メートルの望遠鏡しかありませんでした。
日本が欧米と同じように暗い天体を観測する場合、すばる望遠鏡を使うしかありませんでした。そこで、すばる望遠鏡に天体の探索に向いた主焦点を作ることになったのです。もちろん、主焦点でシャープな像の写真が撮れるようにするためには、望遠鏡・補正レンズ・カメラ、そのどれをとってもさまざまな努力を必要としました。しかし、天文学者と世界最先端の技術を持つ日本のメーカーの力で、見事に主焦点のカメラを立ち上げたのです。そして、実際にこの主焦点を搭載したすばる望遠鏡で天体を探索したところ、4メートル級の望遠鏡で探索するのは難しい暗い天体が次々と見つかり、発見ラッシュの立役者となったのです。振り返ってみれば、もともとは4メートル級望遠鏡がなかったために無理をして作った主焦点でしたが、それが思わぬ好結果を生んだのです。
宇宙、天体観測の道具の進化は次々と新しい発見をもたらしてきた。今に至る天体観測の歴史を紐解くと望遠鏡・補正レンズ・カメラの進化を見てとれる。
宇宙の真の姿とは?最新の天文学と宇宙論は問いかけるくつがえる人類の常識と最前線からの報告。
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




