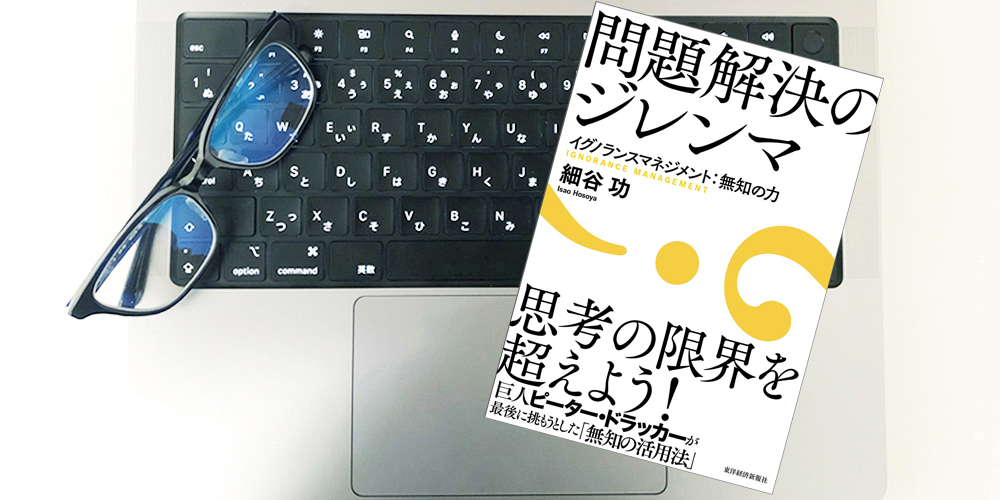
ピーター・ドラッカーは亡くなる前に「書き残したテーマがあるか?」と聞かれ口にした「無知(イグノランス)のマネジメント。もし書いていたら、私の最高傑作になっただろう」とまで言っている。そしてはるか昔ソクラテスは「無知の知」を唱えた。「無知」に気づき、「無知」を活用する「問題発見」のための思考法を体系化!
「メタ認知」が「無知の知」による気づきの原点
一つ目の「無知」への着目点は、「無知の知」である。先にも述べたように、これは自らの無知を「メタ」のレベルで、つまり自分自身を上から見る視点で眺めて認識することである。ここまでの言葉で表現すれば、「未知の未知」をどれだけ意識できるかで勝負が決まる。
メタ認知とは「気づき」のための視点である。気づきがなければその先の進歩は一歩もない。これが問題発見のための「第 0 ステップ」である。「無知の知」がなければすべての思考回路は起動しない。そのためにここまで述べたような無知の様々な側面や種類について十分な自覚を持っている必要がある。
ソクラテスが唱えた「自らが最大の知恵者だとすれば、それは『自らいかに知らないかを自覚している』ことだ」という言葉が、「無知の知」のすべてを物語るだろう。「無知の知」を「無知・未知の次元」の言葉で表現すれば、「自己と他者」という視点の軸をもって「自分自身の存在を相対化する」ことができるかどうかが鍵となる。これは「次元の無知」のうちの特別な(難易度の高い)ケースといえる。自分を客観的に見ることで、「無知の知」の境地に達して思考回路を起動すること。これが最も難しい問題発見の第 0 ステップである。
普通に生きていると案外自分を客観的にみるということはしないのが人間。「無知の知」の境地に辿り着き思考回路を起動することが問題発見・解決の第一歩。「メタ認知」とも呼ばれ広く浸透したこの行動があなたの問題をあぶり出します。
線を引くか、引かないか
このように、「エスタブリッシュメント」としてのアリ型の思考では、ある時点を境に態度が一変する。その原因を探るために、二つの思考回路の違いのもう一つの側面を見てみると、図表 3‐23 に示した思考回路の違いは、本書で繰り返しているとおり、観察対象に対して「線を引く」「線を引かない」の差ともいえる。
「外向きの開いた」思考回路を持つイノベーターとしてのキリギリスは、特異点に対して偏見を持たずにフラットな視点で見ている。そこにそれまでの「常識」と区別する線を引くことはせずに、新しい動きの芽として捉える。それに対して、「内向きの閉じた」思考回路を持つエスタブリッシュメントとしてのアリは、常に新しい事象を、自分が持っている「常識」という線の内側にあるか外側にあるかで判断し、まずは排除して規制、管理にかかるという動きをとる。
つまり、一度抽象化されたルールにこだわって、特異点を発見するのが遅れるのが「内向きの閉じた思考」の特徴といえる。エスタブリッシュメント側の思考回路は、既存のルールにしばられているために、特異点に対して新しい視点を持つタイミングがイノベーターより何歩か遅れ、その見方を捨て去るのも一歩遅れる。
内向きの閉じた思考回路と外向きの外向きの開いた思考回路。アリとキリギリスをこう評してその特徴を見ていく。観察対象について線を引くか否かの差がアリとキリギリスの間には存在し思考回路について語られている。ルールにこだわり新しい視点を持つタイミングが遅れるとその見方を捨て去るのにも遅れが生じる。自己評価をする際の着眼点がここにある。
問題解決のジレンマから解き放たれ思考の限界を越えるための視点を持つための第一歩。
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




