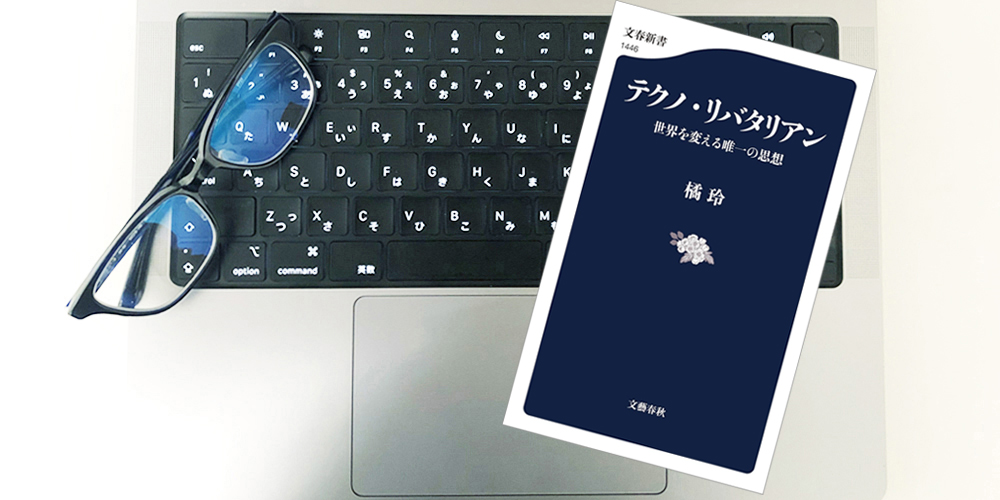
日本のGDPの25%にも及ぶアメリカのIT企業家上位10数名の資産総額。もはや個人が国家レベルの影響力を及ぶす独占の世の中。既存の国家も民主主義も超越した、数学的に正しい統治の実現を望みハイテク自由至上主義とも呼べる哲学を信奉する彼らの影響は今後どのように世界を変えるか?
競争よりも独占
イーロン・マスクはシリコンバレーの多くの進歩主義者と同様に、テクノロジーによって「よりよい世界、よりよい未来」が実現できると素直に信じているリベラルだった。それが「リベラル」や「左派(レフト)」から理不尽な(と本人には思える) 攻撃を受けるなかで、リバタリアンに〝転向〟した。
それに対してティールは筋金入りのリバタリアンで、それと同時に、ルネ・ジラールの教えによって苦い真実を受け入れた。
これまでの自分の人生は、他者の欲望を模倣しようとする無意味な競争だったと思い知ったティールは、自由な市場での熾烈な競争を熱烈に支持する一方で、起業においては、競争は利益を減らす敗者の戦略以外のなにものでもないと考えるようになる。もっとも大きな利益をもたらすのは独占であり、そのためには協力こそが最適戦略なのだ。
だからこそティールは、コンフィニティ(ペイパル) 時代、Xドットコムというライバルが現われ、顧客争奪戦で圧倒できないとわかったとき、経営から身を引いてマスクを合併会社のCEOにする決断ができた。その後、マスクはCEOを解任され、ティールが経営を任されることになるが、この裏切りをマスクが根にもっていないのは、ティールには自分と競争する野心がないことを知っているからだろう(それに対して、テスラの創業者であるマーティン・エバーハードとは、成功の功績をめぐって泥沼の裁判沙汰になっている)。
そんなティールの複雑さがよくわかるエピソードがある。饒舌なマスクとは異なり、ティールはメディアのインタビューをほとんど受けず、自分について語ることはさらに少ないが、その数少ない例外が『ニューヨーク・タイムズ』などに寄稿するジャーナリスト、ジョージ・パッカーによるものだ。
パッカーは全米図書賞を獲得した2013年の"The Unwinding: An Inner History of the New America(巻き戻し 新しいアメリカの内なる歴史)"で、オプラ・ウィンフリー(テレビ司会者)、サム・ウォルトン(ウォルマート創業者)、コリン・パウエル(元国務長官)などの大物からサブプライム危機によって深刻な影響を被ったフロリダ州タンパの無名のひとたちまで、さまざまな人物の物語によって1978年から2012年までのアメリカの変遷を浮き彫りにしようとした(邦訳は『綻びゆくアメリカ』)。ティールはその主要登場人物の一人で、これが自らの半生について率直に語った(おそらく)唯一の記録になった。
独占、寡占状態が続くと競争の理論が通用しなくなり消費者にとっても痛いことになりかねない。高価格帯の商品やサービスが跋扈しそれを受け入れるしか選択肢がない状態は非常に痛い。
「死」を回避したいという究極の欲望
わたしたちの直接の祖先であるホモ・サピエンスは、約 10 万年前のアフリカや中東で死者の埋葬を行なっていた。「死すべき運命(mortality)」を意識して以来、人類はずっと「不死」を夢見てきたが、これまで誰一人として「動物」としての運命から逃れることはできなかった。だが強大なテクノロジーを手にしたいま、「生き物」の限界を超えて死を克服できると考える者たちが現われた。
トランスヒューマニストはほぼ全員が白人の男性で、高い知能を持ち、子どもの頃にSFやアニメ、ファンタジー小説にはまり、「死」や「終末」に対する底知れぬ不安に 苛まれている。
だが、トランスヒューマニストはたんなる 奇矯 な者たちではない。異端の文化人類学者アーネスト・ベッカーは1970年代に、人類の歴史や個人の人生の根底にあるのは、「死」を回避したいという強烈な欲望(あるいは恐怖) だと唱えた。
ベッカーによれば、あらゆる宗教が「死」について語っているのは偶然ではない。「死すべき運命」への恐怖、あるいは「永遠の生」への憧れから、わたしたちの祖先はそのときどきの文化や科学技術の水準によって、死に対処するさまざまな物語や儀式を生み出し、ピラミッド、教会、寺院、モスクなどの巨大建造物をつくってきた。
ベッカーの理論はフロイト主義的(生への欲望であるエロスの対極にある、死への欲望タナトス) だとしてアカデミズムではずっと無視されてきたが、1980年代に若手の心理学者によって再発見された。彼らは実験心理学の手法を使って、わたしたちが「死の恐怖」に強く影響されていることを繰り返し証明した。
よく知られているのが、売春婦に科す保釈金を決定する判事を被験者にした実験だ。判事は偶然を装った同僚から、決定の前に性格質問票に答えるよう求められる。そこにはダミーの質問に混じって、「倫理態度性格調査」の名目で死を思い起こさせる設問が含まれていた。
「自分自身の死を考えたとき、心のうちに生じる感情を簡潔に説明してください」との質問に、ある判事は「あまり考えていないが、私がいなくなってさみしい思いをする家族のために、とても悲しい気持ちになると思う」と答えた。
「あなたの肉体が死ぬとき、そしてあなたが肉体的に死んだ状態になったとき、自分に何が起きると思うか、できるだけ具体的に書き出してください」との質問には、「痛みのトンネルに入ったあと、光のなかへと解き放たれると思う。体は埋められ、やがて地中で腐るが、私の魂は天国に昇り、そこで救い主に会うことがわかる」と書いた。
自殺を図ったことがる人ならわかると思うが、感情が昂り自身が制御できない状況に陥ってことに至る場合がある。後から考えると死ぬほどの辛いことではなくてもその時は真剣。死は救済にならない生きてこそという基本的なことを理解していないとあらぬ方法で人生を曲げることに。
テクノロジーが支配する世界で望ましい生き方とはどういうものかを考える良い機会となる書籍。
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




