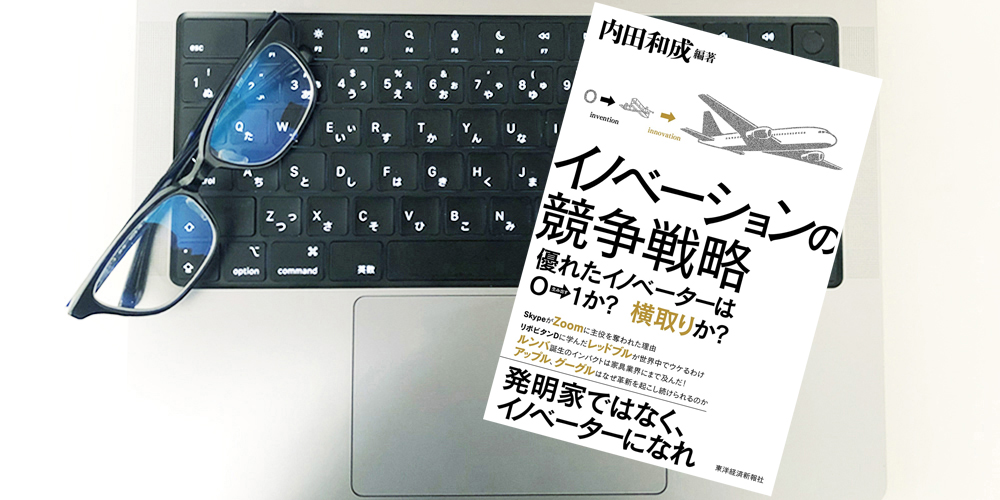
世の中にない新たな発明やサービスを生み出すことは企業のイノベーションの必要条件ではない。必要なのは新しい製品やサービスを浸透させること。これがイノベーションの本質である。イノベータになるための競争戦略がここに集結。
価値を生み出し、日常を変えるのが真のイノベーター
価値のあるものを創造したとしても、それだけで終わることがある。一時的に普及しても継続性がなく終わることもある。たくさんの人たちに使ってもらい、その製品やサービスの周辺にまで影響を及ぼし、不可逆性を持ち得て、はじめて社会変化をもたらすことができたと言えよう。これがイノベーションなのだ、新しいだけではダメなのだ。
最近、家庭内の日常に大きく変化をもたらしたものがある。「ルンバ」だ。実は、英語表記はあまりなじみがないが、つづりは Roomba。 room =部屋と、 rumba =ルンバ(ラテン音楽のダンス)をかけている。ルンバが動いている姿を見ると実にピッタリだ。部屋のアウトライン一杯を使い、まさに踊っているように感じられる。この姿こそ、人々がはじめて買ったロボットであり、家の中に居場所を見つけ、家庭内生産性を大幅に向上させたイノベーションである。
ルンバをつくったコリン・アングルは、小さな頃母を喜ばす最も合理的な方法としてコップを運ぶロボットをつくろうと思いついた。今やその思いが形を変えて、ルンバとなっている。小さな頃はレゴブロックやモノポリーが好きだったようだ。イノベーターが発想したアイデアを振り返るときに、育った環境や与えられた影響をひも解き、達成された要因として取り上げることが多い。イノベーションも基本的には同じである。不可逆性のある大きな変化をもたらした要因は、その製品やサービスの価値以外にもあるのが当然であり、その部分を話さなければ面白くもないし、深みもなければ、正確でもない。
では、ルンバの生まれた時代の背景はどうなっているのであろうか。少子高齢化、生産人口の減少が確実に進んでいく中で、人手不足の解消、過酷な労働からの解放を狙い、ロボット技術が発達してきている。そうしたところで、女性の社会進出が進み家庭内労働の生産性向上が望まれていることが誕生のきっかけとも言える。
しかし、男性社会の中では潜在化しているニーズであったことが、女性の社会進出が進んだことで、ニーズが顕在化し、多くの商品やサービスが誕生しているという解釈のほうが腑に落ちる。背景と実行がつながっているからだ。
掃除は主婦がするものという心理、「自分がだらしない」と思われてしまうのではないかという心理、他にも紙おむつをはかせるなんて手抜きだという心理、オイシックスのミールキットを購入して、火を使って家族に食事を準備しているときに感じる満足感。このようなものは、生活するための製品やサービスなのであり、母の評価軸ではない。人の心は、時代とともに徐々に変化していくものなのだ。
ルンバに合わせて家具を揃える人が出てくるほど生活に溶け込んでいる。まさに人々の生活を変えたイノベーションと言える。
製品的な価値も大切だが、生み出されてきた背景や受け手の心理など、すべての要素がいかに適切に組み合わさり、機を逸することなく歩んできたのかが見えてくる。それが社会に大きな変化を生み出し、不可逆性のある私たちの生活スタイルを変えてしまったのである。
最近暮らしの質が格段と上がる家電やガジェットが多く出回ってて物欲が止まりません。生活に浸透するのはその中でもわずか。中でもスマホ、パソコンはもうないと生きるのが辛いレベルまで浸透してしまって、バッテリーがお亡くなりになって大変な目に遭う前に新機種に買い替えなきゃという衝動に(笑)
読みたい本をいつでもどこでも読めるようにした「 Kindle」
Kindle(キンドル)は、 2007 年にアマゾンが販売を開始した電子書籍リーダーおよび、どのデバイスでも電子書籍を読める無料アプリである。電子書籍は、電子データ化した本を、電子機器で読めるようにしたもので、読みたいと思ったときにすぐに本を買いたいという即時入手欲や、スマートフォンやタブレットの普及で隙間時間を有効に活用したいというニーズが増えてきたことを追い風に広まっている。
電子書籍は、端末本体から書籍をいつでも簡単にダウンロードでき、アプリなどを使用すれば、どの端末でも使用可能である。複数端末間で購入済みの本を同期することもできる。そのためわざわざ本屋に行かなくてもよいし、かさばる本を持ち歩いたり、保管したりする必要がない。この電子書籍業界の中でも Kindle は、プラットフォームの利便性やアマゾンがもつ顧客ベースから、 2021 年時点で業界のトップに君臨している。
最初の電子書籍リーダー「 LIBRIe」
しかし、実は最初の電子書籍リーダーは 2004 年に発売されたソニーの LIBRIe(リブリエ)であった。 Kindle 開発のきっかけは、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が、この LIBRIe を見て衝撃を受け、社内に検討チームを立ち上げたことだとも言われている。
では、なぜ後発者の Kindle が先行者の LIBRIe を追い越し、現在の地位を確立できたのだろうか。
LIBRIe は、 E‐ink 技術を用いて、紙のように読みやすい画面表示を可能にした最初の電子書籍リーダーであったが、通信機能が搭載されていなかった。そのため、パソコン上にインストールしたソフトから電子書籍を購入して、 USB で LIBRIe に電子書籍ファイルを転送する必要があった。さらに、電子書籍を読めるのは、専用デバイスである LIBRIe だけで、閲覧期間は 2 カ月という制限もあった。つまり、わざわざ手間をかけて端末に書籍を移したのに、たった2カ月間しか見られないという、ユーザーにとって使い勝手のよくないものだった。
Kindle開発担当者は、このLIBRIeの課題を見抜き、当初予定にはなかった無線通信機能を搭載したプロトタイプを製作した。Kindleは、通信機能を搭載することで端末単体でも簡単に電子書籍を購入して読める体験をつくり出したのである。またさらに、自社端末以外にもアプリを開放するという戦略をとることによって、どの端末からでも書籍を読めるようにした。
「いつでもどこでもすぐに」購入できる
ベゾス氏は、メディアインタビューで、Kindle開発において、「目指しているのは、どんな本でも、どんな発行者でも、どんな言語でも、60秒で手に入れられるようにすること」、そして「何かをやりたいのであれば、それにかかる負荷や問題を減らすことだ」とコメントしている。
Kindleは革命ですよね。電子書籍は持ち運ぶのに嵩張らないメリットがあります。そして毎日のように本を読む身としては、KindleUnlimitedのサブスクが神レベルのサービスだと思います。新刊は読めませんがそれでも何十万冊といった桁違いな数の書籍が自分の手元にあるのですから。
新しい価値を生み出し、生活の質向上に貢献すること、それが浸透することが新しいサービスやものを売る側として求められること。新製品などは作って終わりではなくそれがマスの支持を取り付けられるかにかかっています。発明家ではなくイノベーターとなれ!
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




