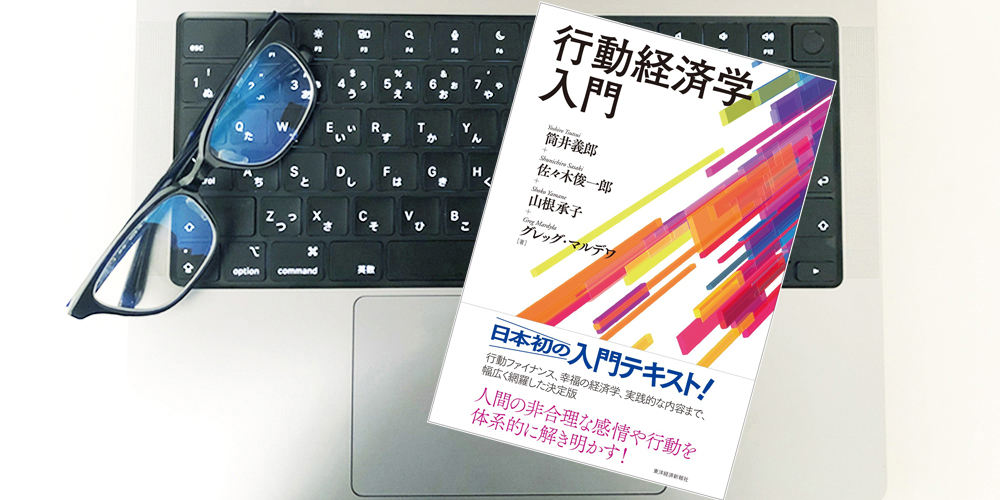
実践的な内容を含む行動ファイナンス・幸福の経済学をはば広くカバーした決定版的書籍。人間の非合理な感情や行動を体系的に解明していきます。
株式プレミアム
株式プレミアム とは、(日経平均のような)株価指数で表される株式市場全体の期待収益率と、債券などで構成される安全資産ポートフォリオの収益率との差である(安全資産とは、リスクがゼロの資産であるが、厳密にリスクがゼロの資産は存在しない。実証分析においては、リスクが小さい国債などを安全資産とみなして分析する)。期待収益率は観察不可能であるため、過去データを用いて株式プレミアムを計測する。米国の株式市場(1889年~1978年)における株式プレミアムは実質(物価上昇率を差し引いて調整したもの)6% であった。一方、合理的な投資家を仮定する理論モデルの多くは、株式プレミアムは1~2% ほどであると推定する ★ 6。したがって、効率的市場仮説を仮定している金融市場の理論モデルは、現実の株式プレミアムの大きさを説明できない。これは株式プレミアムパズルと呼ばれるアノマリーである。
年利6%という数字はやはり投資に値するパーセンテージだと思った。かつての日本では銀行や郵便局に預けているだけでそれだけの年利を約束していた時代もある。その頃はノーリスクでそれだけの年利だったので貯金しているだけで1億貯めるのも造作もないことだった。それが今ではある程度のリスクを取らなければ叶わない年利に。長い年月をモニタリングすると株式市場は魅力的な投資先であることに変わらない。リスクを恐れるならインデックスを買うなど分散投資を主軸に買うといい。
行動経済学を役立てる
行動経済学が解明した事実はどのように役に立つだろうか。第1に、 弱者保護 や 消費者保護 政策に対するこれまでの経済学の考え方に影響を与える。一般社会では弱者保護が国民感情に沿う政策であり、消費者保護政策もそうしたものの1つである。例えば、購入後一定期間ならば購入契約を破棄できるクーリングオフ制度などは、消費者保護の観点から作られている。しかし経済学者は、このような弱者保護政策に冷淡であることが多かった。なぜなら、伝統的な経済学は「人間は合理的である」と考えているため、そもそも「弱者」が存在しないことになるのである。つまり市場原理が正常に働いているならば、個人はそれぞれ合理的に効用最大化を行い、それぞれ最適に振る舞っている。そこには何の問題もない。伝統的経済学の考え方に沿えば、不当な力を追放して、個人をできるだけ自由に判断する環境を整備すれば、あとは放っておけばよい。例えば企業に対しては独占的な市場支配力の排除が重要であるが、それがなされた後は、各企業が自由に行動することによって好ましい結果が得られるだろう。これに対し行動経済学は、個人はいろいろな点で非合理的であり、意志力も弱い存在であると考える。つまり消費者の非合理性に付け込んだ販売がなされれば、消費者は本当は買いたくないものを購入するという事態が発生し得るので、クーリングオフのような消費者保護が必要となる。他にも、リスクのある金融商品が銀行で販売されて一般の人に提供されるようになった時、そのリスクについて詳細に説明することが義務付けられた。また、消費者金融で深刻な多重債務問題が起きた時には金利が引き下げられ、借入額も制限された。
弱者保護政策として、弱者の行動を規制するということも行われる。例えば、振り込め詐欺の多発に対して、ATMでの現金の送金が10万円以下に制限された。麻薬の所持や服用は処罰されるといったことも、弱者保護に含まれる。しかし、非合理的な人の存在がただちにこれらの規制や保護を正当化するわけではない。非合理的な人が存在するからと言って、すべての人が非合理的であるとは限らないからである。例えば、消費者金融からの借り入れには、第3章で説明した双曲割引という非合理性が関連しているが、筒井らは、アンケート調査をもとに、強い双曲割引を持つ人は国民の2割から3割であるとしている★1。つまり残りの約7割から8割の人にとっては、借入制約という規制は望ましくない。規制をかけると市場の効率性が失われ本当に望ましい状態が実現できなくなるので、必要のない人にとって規制はない方がよいのである。このような場合に規制をすべきかどうかは国民の価値判断に委ねられる問題だろう。
行動経済学の出現は、弱者保護や消費者保護に対する従来の経済学の冷淡な態度を変更させるものである。それは世の中の常識的な考え方に近いが、合理的な人と非合理的な人の割合を明らかにすることによって、弱者を保護するための規制をすべきかどうかに示唆を与えるというメリットを持っている。
行動経済学は第2に、教育によって非合理性を矯正すべきかという問題も提起する。例えば日本人はリスクを嫌い、預金以外の金融商品に対する投資が少ないが、これはお金に対するゆがんだ認識に基づいているのかもしれない。その一方で、多額の借金をしたり、ギャンブルにのめりこんだりする人も多い。適切な金融・ファイナンス教育をすれば、こうした社会問題が改善されるかもしれない。
僕も若い頃に秋葉原で可愛いおねーさんについて行って版画を買わされたことがある。センスいいと煽てられてローンを組んで買ったのだが家に帰って冷静になり、結局クーリングオフの手続きをとった。良い救済制度だ。弱者保護の政策や制度も知らなければ助けてもらえない。泣き寝入りする人が多いのも事実。自分の不遇を嘆く前にどのような制度があるのかをチェックすると案外弱者に優しい世界だったりする。もちろん情報弱者には厳しい世の中なのだが。
日本初の行動経済学の入門テキストだそうです。人々の行動がどのように経済につながっているのかを知る面白い学問。経済学の観点から人々の行動を観察すると見えてくる面白い現象の数々を見ていきます。人間の非合理な感情や行動を体系的に解き明かす!
※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。
【サブスク】 Kindle Unlimited
僕が利用している読書コミュニティサイト
【本が好き】https://www.honzuki.jp/




